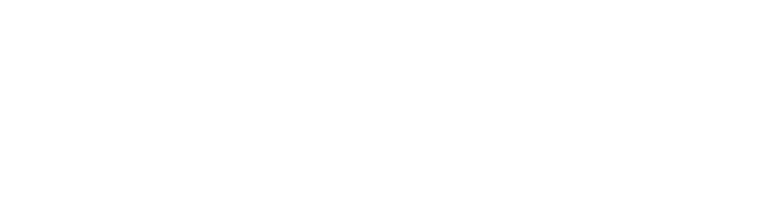Yoshiyuki Yamada
山田 佳之
東海大学医学部
総合診療学系 小児科学
教授

About
1995年に関西医科大学を卒業し、小児科の医師になりました。その後、秋田大学大学院で研究を始めて以来、寄生虫に対する免疫やアレルギー疾患(気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)で重要な「好酸球 Eosinophil」という白血球を中心に研究を行ってきました。その関係で、呼吸器、免疫、血液腫瘍、感染症、消化器と広く分野を横断して研究活動をしてきました。その中でいろいろな出会いやきっかけをいただき、検査を専門とする「臨床検査専門医」となり、また「医学教育」の分野の方々とも仕事をするようになりました。
現在では、好酸球以外に、血液浄化療法の研究や小児の臨床検査の仕事をしており、さらにそこから発展して、昨年は心臓のドックンという「心音」に関する研究でクラウドファンディングを行い、今年は新しい医学教育手法開発のため、「レゴ® シリアスプレイ® ファシリテータ」という資格を取得し、レゴブロックを使ったこの手法の医学教育への導入のため活動を始めました。
興味が多岐に渡り、小児科の範疇に収まらないので、新たにこの「山田佳之研究室」のホームページを立ち上げました。今後の活動をお知らせできればと思っております。
■作成委員長を務めたガイドライン
新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症診療ガイドライン https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00441/
幼児・成人好酸球性消化管疾患診療ガイドライン https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00602/
■研究分野
小児科学、アレルギー・免疫学(特に好酸球学)、臨床検査医学、感染管理
■資格
・医学博士(2003年 秋田大学大学院)
・日本小児科学会専門医・指導医
・日本臨床検査医学会専門医・管理医
・日本アレルギー学会専門医・指導医
・Infection Control Doctor(ICD)
・LEGO® SERIOUS PLAY®トレーニング修了 認定LSPファシリテーター
Member
山田 佳之 (東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
川口 章 (東海大学 医学部医学科 客員教授)
藤井 亮 (東海大学 医学部医学科 客員講師、株式会社Reseablic代表取締役、エンジニア)
落合 成紀 (東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 助教)
柴田 真由子 (東海大学 医学部総合診療学系小児科学 助教)
石塚 一裕 (東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 助教)
犬飼 香織 (東海大学 医学部総合診療学系小児科学 大学院生・臨床助手)
新藤 智子 (東海大学 医学部総合診療学系小児科学 臨時職員)
Research
■消化管アレルギーの病態解明および治療法の開発 (2010 ~ 現在)
2010年度に小児好酸球性食道炎の患者全体像の把握と診断・治療指針の確立に関する研究班(代表)として、厚生労働科学研究補助金を受け、当時、まだ日本ではあまり認知されていなかった疾患である好酸球性食道炎(EoE)を中心に好酸球性消化管疾患(EGIDs)の研究を開始し、その後、成人のEGIDs、新生児・乳児の食物蛋白誘発胃腸症(non-IgE-GIFAs)の研究班と合併し、現在の好酸球性消化管疾患(EGIDs)(野村班)として、診断、治療、病態解明に加え、診療体制構築やガイドライン作成に取り組んできました。特に新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症診療ガイドラインにおいて、それまで、小児消化器と小児アレルギーの分野で必ずしも概念や診療方法が標準化されていなかった本疾患について両方の専門家の考えを集約し、新生児・乳児の食物蛋白誘発胃腸症(国際的にはnon-IgE-GIFAs)として新しく定義し、新しい手法を導入し、エビデンスベースのガイドラインとしたことが初期の活動の重要な部分であったと考えています。その後、わが国に多い非食道好酸球性消化管疾患(non-EoE EGIDs)の実態が明らかになり、治療法の確立が望まれていることが明らかになりました。
研究としては、2014年にnon-EoE EGIDsの多種抗原除去療法が奏功した最初の例を報告し、その後、研究をすすめてきました。群馬県立小児医療センター(山田の前所属)は本疾患群の拠点病院の一つであり、多くの患者様に通院していただいており、研究にもご協力いただいております。
さらに最近では、臨床研究に加え、千葉大学を中心とした多施設との卵黄acute FPIESの共同研究、東京大学との共同研究を含む新生児期・乳児期早期のnon-IgE GIFAsの研究、関西医大、Cincinnati小児病院との共同研究としての小児から成人までのEGIDの研究において、かずさDNA研究所と共同し、プロテオーム解析を進めています。東海大学小児科、群馬県立小児医療センターでは多くの消化管アレルギーの患者様が通院されており、好酸球に関連して、マウスモデルやin vitroでの基礎研究も行える環境を利用して、translational researchを目指しております。
■メンバー(小児科学所属)
・山田 佳之(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
・煙石 真弓(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 講師)
・川村 大揮(東海大学 医学部 総合診療学系 小児科学 助教)
・犬飼 香織(東海大学 医学部 総合診療学系 小児科学 大学院生・臨床助手)
■メンバー(共同研究)
・野村 伊知郎(国立成育医療研究センター好酸球性消化管疾患研究室 室長)
・工藤 孝弘(順天堂大学医学部 小児科・思春期科 先任准教授)
・井上 祐三朗(千葉大学大学院医学研究院 総合医科学 特任准教授)
・佐藤 裕範(千葉大学大学院医学研究院 小児病態学 特任助教)
・川島 祐介(かずさDNA研究所 ゲノム事業推進部 ユニットリーダー)
・渡辺 栄一郎(北里大学医学部 一般小児肝胆膵外科 助教/東京大学医学部 小児外科)
・清水 真理子(群馬県立小児医療センター アレルギー・リウマチ科 部長)
・設楽 佳彦(東京大学医学部附属病院 小児科 助教)
・島谷 昌明(関西医科大学 消化器内科 教授)
・山階 武(関西医科大学 消化器内科 講師)
・Tetsuo Shoda (Division of Allergy and Immunology, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center / UC Department of Pediatrics Assistant Professor)
■LEGO® Serious Play® を応用した医療者(学生含む)の学習・研鑽意欲向上のための動機付け可視化手法の開発 (2023 ~ 現在)
医学生の学習モチベーション向上を目的とした、新たなワークショップを開発しています。
医師国家試験を控えた4〜6年生は、試験への不安やプレッシャーから学習意欲の維持が課題となっています。そこで、自己決定理論に基づいて内的動機づけを強化するワークショップを設計しています。具体的には、レゴ・シリアス・プレイ(LSP)を導入し、学生自らがレゴを用いて目標や動機を形にし、共有する体験を通して自律性や自己効力感を高めることを狙っています。また、ワークショップの前後にアンケート調査を実施し、その効果を定量的および定性的に評価することで、医学生の長期的な学習意欲向上に寄与するとともに、医学教育のみならず他の教育分野にも応用可能な知見の提供を目指しています。本研究は2023年7月に試験的に導入され、2023年10月よりクリニカル・クラークシップ内の授業で実施中です。なお、私はLEGO® SERIOUS PLAY®トレーニングを修了し、認定LSPファシリテーターの資格を取得しております。これまでの経験を活かし、学生の皆さんがより楽しく主体的に学べる環境作りに努めています。


■メンバー(小児科学所属)
・山田 佳之(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
・落合 成紀 (東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 助教)
・石塚 一裕 (東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 助教)
■メンバー(共同研究)
・藤井 亮(株式会社Reseablic代表取締役、エンジニア)
■体外循環および体外循環を用いた血液浄化療法の研究(動物モデル) (2021 ~ 現在)
心臓の手術では、一時的に患者様の血液を体外に取り出し、酸素を加えて再び体内へ戻す「体外循環」という技術が用いられます。これは、人工心肺装置が血液を循環させることで、手術中に心臓や肺の役割を代行する大切な方法です。従来は、ブタやイヌなどの大型動物を用いて研究が行われていましたが、これらは費用や倫理面での課題が多くありました。一方、ラットは体が小さく、取り扱いが容易で費用も低いため、繰り返し実験を行うのに適しており、また人間で試す前の安全性や効果の検証に有用です。
しかしながら、人間に近い体外循環の状態を小さなラットで再現するのは技術的に難しい問題がありました。これまでの研究では、ラットでの長期生存が難しく、実験モデルとしての信頼性が十分に得られなかったのです。本研究では、ラットの体に合わせた人工心肺装置や手術法の小型化・改良に挑戦し、手術後もラットが安定して生存できる実験モデルを確立することを目指しております。例えば、極小のポンプや人工肺を用いることで血液循環を実現し、出血を最小限に抑える技術と組み合わせることで、ラットへの負担を大幅に軽減しております。 この新たなラット実験モデルにより、体外循環中や手術後に体内で起こるさまざまな変化を詳しく観察することが可能となります。具体的には、体外循環中に誘発される炎症反応や各臓器への影響を解析することで、実際の心臓手術後に見られる合併症の予防や軽減につながる知見が得られると期待しております。また、新しい薬剤や治療法の効果をラットで検証することで、心臓や脳を保護するための新たなアプローチの開発にも寄与できると考えております。
本研究は、東海大学医学部小児科と富士システムズ株式会社との共同研究のもと、国内外の研究助成を受けながら進められております。今後も、安全性と有効性を追求した実験を重ね、医療現場での実践に直結する成果を創出することで、先進医療の実現に貢献してまいります。
■メンバー(小児科学所属)
・山田 佳之(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
・川口 章(東海大学 医学部医学科 客員教授)
・新藤 智子(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 臨時職員)
・川口 玄(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 非常勤講師)
・柴田 真由子(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 助教)
・犬飼 香織(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 大学院生・臨床助手)
■メンバー(共同研究)
・富士システムズ株式会社
■一酸化炭素(CO)中毒による心肺停止状態からの人工心肺を用いた拡大蘇生術の研究 (2024 ~ 現在)
本研究では、一酸化炭素(CO)の有害な作用と、適切な管理下で発揮される医療上の有用性の両面に着目しております。
第一の研究は、CO中毒による心肺停止状態からの拡大蘇生術に関するもので、ラットモデルを用いて2000ppmのCO吸入により致死的な中毒状態を再現し、体外循環装置を活用して心肺機能の回復を試みます。従来の酸素療法では十分な効果が得られなかったため、同志社大学が開発したCO除去剤「HemoCD」を併用し、COの速やかな除去とミトコンドリアにおけるエネルギー代謝の回復を図ることで、蘇生成功率の向上および後遺症の軽減を目指しております。
第二の研究は、表在性創傷の治癒促進におけるCOの作用を明らかにする試みです。こちらでは、Prolong社製のCO抱合ポリエチレングリコール修飾ヘモグロビン(SG)をCO供給剤として用いるとともに、HemoCDをCO除去剤として採用し、局所外用および全身投与の方法で創傷治癒への影響を比較検討します。COは血管拡張や抗炎症、さらには抗菌作用を有するため、これらの効果が創傷治癒過程において内的因子を改善し、治癒促進につながると期待されます。
両研究は、COが持つ複雑な生理作用を統合的に理解することで、CO中毒の迅速な解毒法および安全な蘇生術の確立、さらに新たな創傷治癒治療法の開発に寄与することを目的としております。実験は安全対策を十分に講じた上で行われ、最終的には医療現場での実用化が期待される成果となる見込みです。
■メンバー(小児科学所属)
・山田 佳之(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
・川口 章(東海大学 医学部医学科 客員教授)
・川口 玄(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 非常勤講師)
・柴田 真由子(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 助教)
・犬飼 香織(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 大学院生・臨床助手)
・新藤 智子(東海大学 医学部総合診療学系小児科学 臨時職員)
■メンバー(共同研究)
・住吉 秀明(東海大学 医学部医学科基礎医学系生体機能学領域 准教授)
・北岸 宏亮(同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 教授)
■心音による疾患スクリーニングの自動化 (2022 ~ 現在)
心音による疾患スクリーニングの自動化を目指しています。
聴診は患者様に安心感を与え、他の検査手段よりも手軽で扱いやすい初期のスクリーニング手段です。しかし、医師の経験や専門分野によって診断の客観性や信頼性にばらつきが生じる課題があります。既存の研究では、デジタル信号処理や深層学習を用いて心音のみで高精度な診断を目指す試みがありましたが、未解決の問題が多く、臨床医の技術に代わるものではありません。また、一般臨床では心音だけで高精度な診断を必要としない場合も多いです。
そこで、信号の数学的解析に医師の知見を組み合わせ、初期スクリーニングとしての異常検知システムを開発し、低価格で臨床に導入することを目指します。現在、心音をその場で画像化し、患者様に説明できるシステムを構築し、説明手段の拡充に成功しています。波形の画像化自体は新しい技術ではありませんが、臨床に導入し患者様への説明手段が増えたことは大きな意義があります。
■メンバー(小児科学所属)
・山田 佳之(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 教授)
・松田 晋一(東海大学医学部 総合診療学系 小児科学 准教授、小児循環器学)
■メンバー(共同研究)
・道海 秀則(こどもクリニックどうかい院長、小児科医師、産業医)
・藤井 亮(株式会社Reseablic代表取締役、エンジニア)
・猪股 弘明(PHAZOR合同会社代表、精神保健指定医、エンジニア)
■論文:最新5年分(2020 – 2025)
- Dowa Y, Yamada Y, Kato M, Matsumoto N, Kama Y, Shiihara T. Sweet Potato Was Not So Sweet: Undetected Foreign-body Aspiration in a Healthy Child Leading to Acute Bronchial Asthma. Tokai J Exp Clin Med. 2019;44:1-4.
- Kobayashi Y, Konno Y, Kanda A, Yamada Y, Yasuba H, Sakata Y, et al. Critical role of CCL4 in eosinophil recruitment into the airway. Clin Exp Allergy. 2019;49:853-60. doi: 10.1111/cea.13382. Epub 2019 Mar 29.
- Yagi H, Takizawa T, Sato K, Inoue T, Nishida Y, Ishige T, et al. Severity scales of non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies in neonates and infants. Allergol Int. 2019;68:178-84. doi: 10.1016/j.alit.2018.08.004.
- Kama Y, Kato M, Yamada Y, Koike T, Suzuki K, Enseki M, et al. The Suppressive Role of Streptococcus pneumoniae Colonization in Acute Exacerbations of Childhood Bronchial Asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2020;181:191-9. doi: 10.1159/000504541.
- Koizumi A, Maruyama K, Ohki Y, Nakayama A, Yamada Y, Kurosawa H, et al. Prevalence and Risk Factor for Antibiotic-resistant Escherichia coli Colonization at Birth in Premature Infants: A Prospective Cohort Study. Pediatr Infect Dis J. 2020;39:546-52. doi: 10.1097/INF.0000000000002623.
- Matsuda S, Kato M, Koike T, Kama Y, Suzuki K, Enseki M, et al. Differences in Virus Detection and Cytokine Profiles between First Wheeze and Childhood Asthma. Tokai J Exp Clin Med. 2020;45:10-7.
- Miyamoto T, Ozaki S, Inui A, Tanaka Y, Yamada Y, Matsumoto N. C1 esterase inhibitor in pediatric cardiac surgery with cardiopulmonary bypass plays a vital role in activation of the complement system. Heart Vessels. 2020;35:46-51. doi: 10.1007/s00380-019-01466-2.
- Shimizu A, Ebara Y, Nomura S, Yamada Y. Chronological changes in strawberry tongue in toxic shock syndrome toxin-1-mediated Exanthematous Disease. J Gen Fam Med. 2020;21:280-1.
- Shimizu A, Tsukagoshi H, Sekizuka T, Kuroda M, Koizumi A, Fujita M, et al. Meningitis and bacteremia by nonhemolytic Group B Streptococcus strain: A whole genome analysis. Microbiol Immunol. 2020;64:630-4. doi: 10.1002/jgf2.376.
- Watanabe S, Yamada Y, Murakami H. Expression of Th1/Th2 cell-related chemokine receptors on CD4(+) lymphocytes under physiological conditions. Int J Lab Hematol. 2020;42:68-76. doi: 10.1111/ijlh.13141.
- Yagi H, Sato K, Arakawa N, Inoue T, Nishida Y, Yamada S, et al. Expression of Leucine-rich Repeat-containing Protein 32 Following Lymphocyte Stimulation in Patients with Non-IgE-mediated Gastrointestinal Food Allergies. Yale J Biol Med. 2020;93:645-55.
- Yagi H, Takizawa T, Sato K, Inoue T, Nishida Y, Yamada S, et al. Interleukin 2 receptor-alpha expression after lymphocyte stimulation for non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies. Allergol Int. 2020;69:287-9. doi: 10.1016/j.alit.2019.11.003.
- Yamada Y. Unique features of non-IgE-mediated gastrointestinal food allergy during infancy in Japan. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2020;20:299-304. doi: 10.1097/ACI.0000000000000642.
- Yoshihara A, Sekine R, Yamada Y, Takai M. Study on polyethylene glycol cross-linker in peptide-conjugated antibody on efficiency of cell capture and release. Anal Biochem. 2020;602:113790. doi: 10.1016/j.ab.2020.113790.
- Ebara Y, Shimizu A, Nomura S, Nishi A, Yamada Y. Mallory-Weiss syndrome complicated by severe aspiration pneumonitis in an infant. Oxf Med Case Reports. 2021;2021:omab094. doi: 10.1093/omcr/omab094.
- Shimizu A, Shimizu M, Nomura S, Yamada Y. Pyomyositis as a manifestation of late-onset group B Streptococcus disease. Pediatr Int. 2021;63:1400-2. doi: 10.1111/ped.14632.
- Yamamoto M, Nagashima S, Yamada Y, Murakoshi T, Shimoyama Y, Takahashi S, et al. Comparison of Nonesophageal Eosinophilic Gastrointestinal Disorders with Eosinophilic Esophagitis: A Nationwide Survey. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:3339-49 e8. doi: 10.1016/j.jaip.2021.06.026.
- Dellon ES, Gonsalves N, Abonia JP, Alexander JA, Arva NC, Atkins D, et al. International Consensus Recommendations for Eosinophilic Gastrointestinal Disease Nomenclature. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022;20:2474-84 e3. doi: 10.1016/j.cgh.2022.02.017.
- Kama Y, Yamada Y, Koike T, Enseki M, Hirai K, Mochizuki H, et al. Allergic Sensitization Is Crucial for the Suppressive Role of Streptococcus pneumoniae in the Acute Exacerbation of Asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2022;183:1270-80. doi: 10.1159/000526408.
- Kama Y, Yamada Y, Koike T, Suzuki K, Enseki M, Hirai K, et al. Antibiotic Treatments Prolong the Wheezing Period in Acute Exacerbation of Childhood Bronchial Asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2022;183:617-27. doi: 10.1159/000521192.
- Maeda M, Kuwabara Y, Tanaka Y, Nishikido T, Hiraguchi Y, Yamamoto-Hanada K, et al. Is oral food challenge test useful for avoiding complete elimination of cow’s milk in Japanese patients with or suspected of having IgE-dependent cow’s milk allergy? Allergol Int. 2022;71:214-20. doi: 10.1016/j.alit.2021.09.001.
- Murai H, Irahara M, Sugimoto M, Takaoka Y, Takahashi K, Wada T, et al. Is oral food challenge useful to avoid complete elimination in Japanese patients diagnosed with or suspected of having IgE-dependent hen’s egg allergy? A systematic review. Allergol Int. 2022;71:221-9. doi: 10.1016/j.alit.2021.09.005.
- Tomizawa H, Yamada Y, Arima M, Miyabe Y, Fukuchi M, Hikichi H, et al. Galectin-10 as a Potential Biomarker for Eosinophilic Diseases. Biomolecules. 2022;12. doi: 10.3390/biom12101385.
- Arakawa N, Yagi H, Shimizu M, Shigeta D, Shimizu A, Nomura S, et al. Dupilumab Leads to Clinical Improvements including the Acquisition of Tolerance to Causative Foods in Non-Eosinophilic Esophagitis Eosinophilic Gastrointestinal Disorders. Biomolecules. 2023;13. doi: 10.3390/biom13010112.
- Iijima H, Odagiri K, Yamamoto S, Murakami T, Uchiyama A, Yamada Y, et al. X-linked Agammaglobulinemia Diagnosed Following Bezold’s Abscess: A Case Report. Tokai J Exp Clin Med. 2023;48:72-7.
- Kram YE, Sato M, Yamamoto-Hanada K, Toyokuni K, Uematsu S, Kudo T, et al. Development of an action plan for acute food protein-induced enterocolitis syndrome in Japan. World Allergy Organ J. 2023;16:100772. doi: 10.1016/j.waojou.2023.100772.
- Suzuki H, Morisaki N, Nagashima S, Matsunaga T, Matsushita S, Iino A, et al. A nationwide survey of non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies in neonates and infants. Allergol Int. 2023. doi: 10.1016/j.alit.2023.10.003.
- Yamada Y. Recent topics on gastrointestinal allergic disorders. Clin Exp Pediatr. 2023;66:240-9. doi: 10.3345/cep.2022.01053.
- Yano H, Koike T, Shibata M, Sugishita Y, Kawabata N, Fujita S, et al. Successful Emergency Decompressive Laminectomy for Burkitt Lymphoma with Metastatic Spinal Lesions: A Case Report. Tokai J Exp Clin Med. 2023;48:52-5.
■共同研究・競争的資金等の研究課題(2023年度の消化管アレルギー関連のみ)
日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究C (一般)、マイクロファイバー細胞分離を用いた消化管アレルギーとその関連疾患の病態解明(研究代表者)、2021.4.1~2024.3.31
消化管アレルギーでの免疫細胞をより詳細に解析するために、これまで用いてきたフローサイトメトリーでの解析に加えて、マイクロファイバーを用いた新しい分子や細胞分離手法を取り入れて、基礎的・臨床的な研究を進めています。
厚生労働省厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患政策研究事業)、好酸球性消化管疾患、診療ガイドラインの改訂と、国際的な疾患サブグループ名の整備に関する研究 (研究代表者:野村伊知郎)、2023.4.1~2026.3.31
2018年、2020年にそれぞれ公開された新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症診療ガイドライン、幼児・成人好酸球性消化管疾患診療ガイドラインの改訂作業などを行なっています。
公益社団法人ニッポンハム食の未来財団、好酸球性消化管疾患、慢性炎症の原因特定のための食物負荷試験標準化に関する研究(研究代表者:野村伊知郎)、2023.4.1~2024.3.31
消化管アレルギー関連の食物経口負荷試験(OFC)は、通常の食物アレルギーでのOFCと食物蛋白誘発胃腸炎症候群(FPIES)のOFCでは確立されたものがありますが、他の新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症や好酸球性消化管疾患については、原因食物の連日摂取で発症することも多く、OFCの方法の確立が望まれています。方法を確立するために研究をしています。
Resume
関西医科大学卒業
関西医大付属男山病院 小児科医員
関西医科大学小児科 助手
秋田大学医学部付属病院 中央検査部医員
秋田大学大学院医学研究科修了
米国シンシナティ小児病院医療センター 博士研究員
群馬県立小児医療センター アレルギー感染免疫・呼吸器科 医長(2008年 部長)
同センター 外来診療部長・地域医療連携室長
同センター 感染対策室長および医局長(兼務)
Award
関西医科大学小児科温仁会 松村賞
米国アレルギー喘息免疫学会 MAAI Best abstract賞
国際好酸球シンポジウム Best abstract賞
安田医学記念財団 医学奨励賞
Contact
〒259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143
東海大学医学部 総合診療学系 小児科学
山田 佳之
TEL: 0463-93-1121
FAX: 0463-94-3426